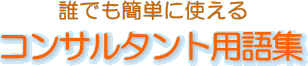�u���s�v�̃R���T���^���g�p��ł��B�p����N���b�N���Ă������������B
|
| �œK�� | |
| �@��� | |
| �@�œK���Ƃ́A����ړI�̂��߂Ɍ�����œK�̏�Ԃɂ��邱�Ƃ������܂��B�u�헪�̍œK���v�A�u�g�D�̍œK���v�A�u���V�X�e���̍œK���v�ȂǁA�R���T���^���g�Ɍ��炸�A�����r�W�l�X�̒��ő��p�����p��ł��B�������A�����̏ꍇ�A����ړI�Ƃ���œK���Ȃ̂��悭�킩��܂���B �@�Ⴆ�Όo�c�҂��悭�u�T�v���C�`�F�[���̍œK����ڎw���v�Ȃǂƌ����܂����A����͌o�c�҂ɂƂ��Ă̍œK���Ȃ̂��A�ڋq�ɂƂ��Ă̍œK���Ȃ̂��͕s���ł��B�g�p����ꍇ�͖ړI��m�ɂ��Ă���g���܂��傤�B |
|
| �@�g���� | |
| �F�c��ے� | �u�헪�𐬌������邽�߂ɍł��K�v�Ȃ��Ƃ͉��ł����H�v |
| �փR���T�� | �u�l�ނƑg�D���œK���ł��B�v |
| ��c������ | �u���������H�v |
| �փR���T�� | �u���݂̏�Ԃ��œK�̏�Ԃɂ��邱�Ƃł��B�v |
| ��c������ | �u�����ł����E�E�E�Ȃ���āI�v |
| �V�l���[�R | �i�]�݂��̍œK�����K�v�E�E�E�j |
| ���t�o | |
| �T�X�e�i�r���e�B | |
| �@��� | |
| �@�T�X�e�i�r���e�B�Ƃ́A��Ƃ������ɂ킽���đ�������\���̂��ƂŁA���{��ł́h�����\���h�ƌ����܂��B �@��Ƃ��������Ă������߂ɂ͗��v���K�v�Ȃ��Ƃ͌����܂ł�����܂��A�T�X�e�i�r���e�B�͗��v�┄��Ȃǂ̌o�ϖʂ����ł͂Ȃ��A���ی��Љ�v���A�@�ߏ���A�K�o�i���X�ȂNJ�Ƃ̎Љ�I��������ϗ����ɂ��d�_��u���������\���Ƃ����Ӗ��Ŏg���Ă��܂��B�Ȃ̂ŁA��ʓI�ɂ͂b�r�q�i��Ƃ̎Љ�I�ӔC�j�Ƃقړ����悤�ȃC���[�W�Ŏg���邱�Ƃ������悤�ł��B �@ �@��Ƃ̗ϗ������傫�������悤�ɂȂ��������A���Ă͗��v�����`�������A���O���T�N�\���n�̐l���������A�u���v�������邾���ł͊�Ƃ͑����ł��܂����v�ƌ����悤�ɂȂ��Ă��܂����B |
|
| �@�g���� | |
| �F�c��ے� | �u�����A��Ƃ͗��v�������邾���ł͑����ł��Ȃ��ƌ�����悤�ɂȂ��Ă��܂����ˁB�v |
| �փR���T�� | �u���̂Ƃ���ł��B�����痘�v���グ�Ă��Ă��Љ�I��������ϗ��ς����@���Ă�����T�X�e�i�r���e�B�������Ɣ��f����܂��B�v |
| ��c������ | �u�����ĂȂт�Ă��E�E�E�H�v |
| �V�l���[�R | �i�Z�N�n���E�E�E�j |
| ���t�o | |
| �V�[�E�A�[���E�G���i�b�q�l�j | |
| �@��� | |
| �@�b�q�l�Ƃ́A�J�X�^�}�[�E�����[�V�����V�b�v�E�}�l�W�����g�iCustomer Relationship Management�j�̗���ŁA��Ƃ��ڋq��l�ЂƂ�ƒ����I�ȊW���\�z���A�ڋq�̃j�[�Y�ɍ��������i�E�T�[�r�X����邱�ƂŌڋq�����x�����ߎ��v�����ڎw����@�������܂��B�v����ɁA�ڋq���͂�����œ������Ȃ����߂̎d�g�݂��b�q�l�ł��B �@�b�q�l�����{���邽�߂ɂ́A�ڋq�f�[�^�x�[�X�A��������Ǘ��A�R�[���Z���^�[�Ȃǂh�s�Z�p���s���Ȃ��߁A�r�W�l�X�n���h�s�n�̃R���T���^���g�����ӂȕ���ł��B�������A�R���T���^���g�̂����Ƃ���ɂb�q�l���\�z����Ɣ���Ȕ�p���������Ă��܂����Ƃ������̂ł����ӂ��������B |
|
| �@�g���� | |
| �F�c��ے� | �u�ŋ߁A���q�������Ɏ���邱�Ƃ�������ł����A�����������@�͂���܂��H�v |
| �փR���T�� | �u�b�q�l�����Ă݂Ă͂ǂ��ł��傤���B�v |
| ��c������ |
�u�������[�邦�ށE�E�E�H�v |
| �փR���T�� | �u�ڋq���͂�����œ������Ȃ����߂̎d�g�݂̂��Ƃł��B�v |
| ��c������ | �u�͂�����œ������Ȃ��E�E�E�H�L�h�S���ň͂�ŁA�d�C�ł������̂��E�E�E�H�v |
| �V�l���[�R | �i��m�c���ˁE�E�E�j |
| ���t�o | |
| �V�[�E�G�X�E�A�[���i�b�r�q�j | |
| �@��� | |
| �@�b�r�q�Ƃ́ACorporate Social Responsibility�̗���ŁA�u��� �̎Љ�I�ӔC�v�Ɩ�܂��B�������Љ�I�ӔC�Ƃ����Ă��A���v���グ��Ƃ��ٗp��n�o����Ȃnjo�ϖʂ̐ӔC�����A���ی�A�Љ�v���A�@�ߏ���A�K�o�i���X�A���S�ȘJ�����ȂǎЉ�I��������ϗ��ʂɂ�����ӔC���w�����Ƃ������A�T�X�e�i�r���e�B�i��Ƃ̎����\���j�Ƃ������t�Ɠ����C���[�W�Ŏg����邱�Ƃ������悤�ł��B �@�����A��Ƃ̃��������傫�������悤�ɂȂ������Ƃɉ����āA�r�q�h�t�@���h�i�Љ�I�ӔC�t�@���h�j�Ⓤ����ɂb�r�q������t�@���h�}�l�[�W���[�������Ă��邽�߁A���{�ł��b�r�q����T�X�e�i�r���e�B���s���ĎЉ�I���S�����o�q�����Ђ������Ă��܂����B�������A���̓��e�Ǝ��Ԃ���������Ă����Ђ�������������݂����ł����ǂˁB |
|
| �@�g���� | |
| �F�c��ے� | �u�܂��܂��A��Ƃ̎Љ��ϗ��ς��d�v�������悤�ɂȂ��Ă��܂����ˁB�v |
| �փR���T�� | �u�����ł��ˁB�b�r�q�͌o�c�ɕs���ȗv�f�ɂȂ��Ă��܂����B�v |
| ��c������ | �u�����������[��E�E�E�H�v |
| �փR���T�� | �u��Ƃ̎Љ�I�ӔC�̂��Ƃł��B�v |
| ��c������ | �u�Љ�I�ӔC�E�E�E�H�@���������A�ӔC�͕����܂���E�E�E�Ȃ���āI�v |
| �V�l���[�R | �i��Ȃ݂̃M���O�ˁE�E�E�j |
| ���t�o | |
| ���ƃh���C�� | |
| �@��� | |
| �@���ƃh���C���Ƃ͎��Ɗ������s���̈�̂��Ƃł��B�����g�h���C���h�Ƃ������Ƃ�����܂����A�C���^�[�l�b�g�̃h���C���ƕ���킵���̂Łg���ƃh���C���h�ƌ������Ƃ������悤�ł��B �@��ƂɎ��ƃh���C�����K�v�ȗ��R�́A�������鎖�ƕ�����K�肷�邱�ƂŖ��d�ȑ��p����}�����A���ƓW�J�̕������w�����邱�ƂŁA�o�c�����ƎЈ��̃x�N�g���������֏W�������邱�Ƃɂ���܂��B�m�d�b���b���b�i�R���s���[�^�ƃR�~���j�P�|�V�����j�����ƃh���C���Ƃ������ƂŁA�]���̒ʐM���Ƃ���R���s���[�^�┼���̎��Ƃi�o�������������Ƃ͗L���ł��B �@�������A�ŋ߂ł͎��ƃh���C������O�ꂽ�l���`��Ɩ���g���p�ɂɍs����̂ŁA��ǂ��Ŏ��ƃh���C����ݒ肷���Ђ������Ȃ��Ă���悤�ł��B �@�Ȃ��A���ƃh���C���̐ݒ���@�͓��T�C�g���o�c�헪����}�j���A���ɁA����Ƃ̎��ƃh���C���f�[�^������ƌo�c�헪�f�[�^�x�[�X�Ɍf�ڂ��Ă��܂��B |
|
| �@�g���� | |
| �F�c��ے� | �u�V�K���ƂƂ��ċ��Z�r�W�l�X���l���Ă��܂��B�v |
| �փR���T�� | �u���ƃh���C������O�ꂽ���Ƃ͐�������m���͒Ⴍ�Ȃ�܂��E�E�E�v |
| ��c������ | �u���ƃh���C������O��鎖�Ƃ̓_���C���E�E�E�Ȃ���āI�v |
| �V�l���[�R | �i�����̃_�W�����͑S�R�_���C���E�E�E�j |
| ���t�o | |
| �V�i�W�[ | |
| �@��� | |
| �@�V�i�W�[�Ƃ́A������ʂ̂��ƂŁA������l���`�̂Ƃ��ɂ悭�g�p�����p��ł��B�Ⴆ�Q�Ђ̍������P�{�P���Q�ȏ�̌��ʂޏꍇ�A�V�i�W�[������ƌ����܂��B�V�i�W�[���ʂƂ������܂��B �@�@�܂��A�V�i�W�[��������ŏ����獇�����l���`�����Ȃ��������ł����A�V�i�W�[������Ǝv���Ă���Ă݂��疳��������A�ŏ�����V�i�W�[���������Ƃ��킩���Ă��Ă�������Ⴄ�A�Ȃ�Ď������\����܂��B |
|
| �@�g���� | |
| �F�c��ے� | �u�����㊔�����������Ă��܂��B�ǂ���������ł��傤�H�v |
| �փR���T�� | �u�����ɍ������V�i�W�[���������Ȃ��Ƃ����܂���ˁB�v |
| ��c������ | �u���Ȃ����E�E�E�H�v |
| �V�l���[�R | �i����̂��F�B�E�E�E�H�j |
| ���t�o | |
| ���{�R�X�g | |
| �@��� | |
| �@���{�R�X�g�Ƃ́A�����B���邽�߂̃R�X�g�̂��ƂŁA���z�ł͂Ȃ����i���j�ŕ\����܂��B���{�R�X�g�͕����{�R�X�g�Ɗ��厑�{�R�X�g�ɕ������A�����{�R�X�g�Ƃ͎ؓ�����ЍȂǂ̗L���q���̗��q���̂��ƂŁA���厑�{�R�X�g�͓����Ƃ��v��������Ҏ��v�����̂��Ƃ������܂��B �@�����Ƃ��v��������Ҏ��v���i�����厑�{�R�X�g�j�Ƃ����̂́A�����Ƃ������Ђ̊������ہA�Œች���̎��v������Ζ�������̂����A�b�`�o�l�i�L���b�v�G���j�Ƃ������_�Ɋ�Â��Čv�Z�������̂ł��B�����{�R�X�g�̂悤�Ɋ�Ƃ����ۂɊO���Ɏx������p�ł͂��ł͂���܂��A���傩�璲�B���������̃R�X�g�Ƃ��Ă݂Ȃ��Ƃ����l�����ł��B �@���̕����{�R�X�g�Ɗ��厑�{�R�X�g��L���q���Ɗ��厑�{�̔䗦�ʼn��d���ς������̂����d���ώ��{�R�X�g�i�v�`�b�b�@���b�N�j�Ƃ����A��Ƃ͓����Ƃ̉��l��ʑ������Ȃ����߂ɂv�`�b�b�ȏ�̗��v�����グ�Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ƃ����̂������̌o�c�̍l�����ł��B���̂v�`�b�b���c�b�e�i�f�B�X�J�E���g�E�L���b�V���E�t���[�j�@�ɂ����Ɖ��l�̎Z�o���d�u�`�̌v�Z�ɂ��g�p����܂� �@�Ȃ��A���厑�{�R�X�g�̎Z�o�ɂ́A�g�s��S�̂̎��v���h�Ƃ��g�����̃x�[�^�l�h�Ƃ����A�l������v�Z���@�ɂ���Ēl���ς��Ă��܂����Ӑ��̂��鐔�l���g���Ƃ����d��Ȗ�肪����܂��B�܂�A���{�R�X�g�͂�����x�Ȃ�Ӑ}�I�ɑ��삷�邱�Ƃ��\�Ȃ�ł����A���̂��Ƃ�m���Ă��m�炸�������̌o�c�ł͂悭���p����Ă��܂��B |
|
| �@�g���� | |
| �F�c��ے� | �u�ŋ߁A���{�R�X�g���ӎ������o�c���K�v�ƌ����Ă��܂��ˁB�v |
| �փR���T�� | �u���{�R�X�g�͊�Ɖ��l��d�u�`�ɉe������̂ŁA��Ϗd�v�Ȏw�W�ł��B��Ƃ����{�R�X�g�ȏ�̗��v���グ�邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�܂��B�v |
| ��c������ | �u���ق��ƁE�E�E�H�v |
| �փR���T�� | �u�����B���邽�߂̃R�X�g�̂��Ƃł��B�v |
| ��c������ | �u�����̒��B�R�X�g�E�E�E�H�����̒��B���x���R�X�g�A�낭�Ȃ��Ƃ͂���܂���E�E�E�Ȃ���āI�v |
| �V�l���[�R |
�i�}�l�[�ɂ��}�i�[���E�E�E�ˁj |
| ���t�o | |
| �X�E�H�b�g�i�r�v�n�s�j���� | |
| �@��� | |
| �@�r�v�n�s���͂Ƃ́A��Ƃ̋��݁iStrength�j�A��݁iWeakness�j�A�@��iOpportunity�j�A���ЁiThreat�j�m�ɂ��邱�Ƃ������܂��B�헪�𗧈Ă���ۂ͕K���ƌ����Ă����قǓo�ꂷ��̂ŁA��x�͕��������Ƃ͂���Ǝv���܂��B �@���Ȃ݂ɁA���������J����ہA����W���X�_�b�N�͏��\�����ށi�U�̕��j�̒��ŁA�r�v�n�s���͂̒�o���`���t���Ă��܂��B�ŋ߂ł́A��ƕ��͂Ɍ��炸�A�X�|�[�c��l���]���̕���ł��g�p����Ă���悤�ł��B �@���̕��͌��ʂ̗��p���@�́A���݂͊������A��݂͕₢�A�@��͊��p���A���Ђɂ͑R���Ȃ����Ƃ������ƂȂ�ł����A�܂�������O�Ȃ��Ƃł��B �@�Ȃ��A�r�v�n�s���͂̂����͓��T�C�g���헪����c�[���i�t���[�����[�N�j�y�[�W�ɁA���������Ƃ�SWOT�����Ɍf�ڂ��Ă��܂��B |
|
| �@�g���� | |
| �F�c��ے� | �u����c���̎��͉�������ł����H�v |
| �փR���T�� | �u�r�v�n�s�������s���܂��B�v |
| ��c������ | �u������ƂԂ��E�E�E�H�v |
| �V�l���[�R | �i����ς�k�l�̌��ˁE�E�E�j |
| ���t�o | |
| �X�L�[�� | |
| �@��� | |
| �@�X�L�[���Ƃ́A�v����@�̘g�g�݂̂��Ƃł��B�ʂ̌v����@�̓X�L�[���Ƃ͌����܂���B�Ⴆ�u�������X�L�[���v�ƌ����A����ʂ̖����������邾���̑Ή���ł͂Ȃ��A���̖������ɂ����p�ł���g�g�݂̂��Ƃ������܂��B�Ȃ��A�X�L�[������邱�Ƃ��u�X�L�[����g�ށv�ƌ����܂��B �@�X�L�[���Ƃ����\���͐��Ƃ��ۂ���������̂ŁA�R���T���^���g�͍D��Ŏg���܂��B�������A�X�L�[���ƌ����Ȃ���A�P�Ȃ�v���Ή������肷�邱�Ƃ��قƂ�ǂł��B |
|
| �@�g���� | |
| �F�c��ے� | �u�s���̒��ŏ����g�ɂȂ邽�߂ɕK�v�Ȃ��Ƃ͉��ł����H�v |
| �փR���T�� | �u�V���ȃ}�[�P�b�g�����邱�Ƃł��B�ڋq�����Ǝ҂��l���ĂȂ����̂������Ă������ƁA�����Ă���ɉ�������r�W�l�X�E�X�L�[����g�ނ��Ƃ��ł��Ȃ���Ώ����Ƃ͂ł��܂���B�v |
| ��c������ | �u�����[�ނ����ށE�E�E�H�v |
| �փR���T�� | �u�g�g�݂����Ƃ������Ƃł��B�v |
| �V�l���[�R | �i��H����́E�E�E�H�j |
| ���t�o | |
| �X�e�[�N�z���_�[ | |
| �@��� | |
| �@�X�e�[�N�z���_�[�Ƃ́A��Ƃ̊����Ɋւ�荇�����ׂĂ̊W�҂̂��ƂŊ���A�����ƁA���Z�@�ցA�ڋq�A�����A�Ј��A�s���A�n��Z���Ȃǂ��X�e�[�N�z���_�[�ł��B���{��ł́h���Q�W�ҁh�ƌ����܂��B �@�����A�X�e�[�N�z���_�[���d�������o�c���d�v�ƌ����Ă��܂����A���߂�ΐ��̒��̂قƂ�ǂ̐l���X�e�[�N�z���_�[�ɂȂ�̂ŁA�������������d������̂��悭�킩��Ȃ��Ȃ����Ⴂ�܂��ˁB |
|
| �@�g���� | |
| �F�c��ے� | �u�����A����₨�q�������łȂ��A�n��Z���Ƃ̊W���厖�ɂ����Ƃ������Ă��܂����ˁB�v |
| �փR���T�� | �u���ׂĂ��X�e�[�N�z���_�[�Ƃ̊W���d�����Ă������Ƃ����߂��܂��B�v |
| ��c������ | �u���ׂĂ̂��Ă����ق邾���Ƃ̊W���d�����Ă������Ƃ����߂��܂��E�E�E�Ȃ���āI�v |
| �V�l���[�R | �i�����Ƃ̊W�����Ă������Ƃ����߂��܂��E�E�E�j |
| ���t�o | |
| �����}�g���b�N�X | |
| �@��� | |
�@�����}�g���b�N�X�Ƃ́A�A���}�̂悤�Ɋ�Ƃ��������邽�߂̂S�̑I�����������t���[�����[�N�ł��B�č��̌o�c�w�҃A���]�t�ɂ���Ē��ꂽ���߁A�u�A���]�t�̐����}�g���b�N�X�v�܂��́u�A���]�t�̐����x�N�g���v�Ƃ��Ă�܂��B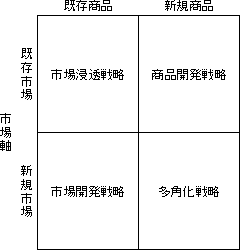 �@��ʓI�ɁA�����̃v���Z�X�͎s��Z���헪�����i�J���헪���s��J���헪�����p���헪�̏��Ԃ��悢�ƌ����Ă��܂����A�ŋ߂̃x���`���[��Ƃ͎s��Z���������ɂł��Ă��Ȃ������ɁA�����Ȃ�l���`�ő��p�������Ⴄ���Ƃ������Ȃ��Ă��܂��B |
|
| �@�g���� | |
| �F�c��ے� | �u�����헪���l���邤���łŎQ�l�ɂȂ�t���[�����[�N�͂���܂��H�v |
| �փR���T�� | �u�L���Ȃ̂̓A���]�t�������}�g���b�N�X�ł��B�v |
| ��c������ | �u�܂Ƃ�������E�E�E�H�v |
| �փR���T�� | �u��Ƃ��������邽�߂̂S�̑I�������������̂ł��B�v |
| �V�l���[�R | �i�R�ڂŏI������Ǝv�������ǁA�S�ڂ�����̂ˁE�E�E�j |
| ���t�o | |
| �헪�I�v�V���� | |
| �@��� | |
| �@�헪�I�v�V�����Ƃ́A�헪�̑I�����̂��ƂŁA���{��ł́h�헪��ֈāh�ƌ����܂��B �R���T���^���g���u�헪�����肷�邽�߂ɂ͕����̃I�v�V�����i�I�����j��p�ӂ��āA���̒�����œK�Ȃ��̂�I�тȂ����v�Ƃ������Ƃ�������鎞�Ɏg���p��ł��B����Ȃ��Ƃ������������Ȃ��Ă�����Ǝv���܂����E�E�E |
|
| �@�g���� | |
| �F�c��ے� | �u�v���W�F�N�g�̑�R�t�F�[�Y�͉��������ł����H�v |
| �փR���T�� | �u�헪�I�v�V�������������܂��B�v |
| ��c������ | �u�헪���Ղ����E�E�E�H�v |
| �փR���T�� | �u�헪�̑I�����̂��Ƃł��B�v |
| ��c������ | �u�I�������点�����Ȃ����E�E�E�Ȃ���āI�v |
| �V�l���[�R | �i�x�^�ˁE�E�E�j |
| ���t�o | |
| �\�����[�V���� | |
| �@��� | |
| �@�\�����[�V�����Ƃ́A�킪���̃r�W�l�X�E�ōł��g�p�p�x�̍����o�Y���[�h�ŁA�ǂ��ɂł��g����֗��ȗp��ł��B�\�����[�V�����́u�����������邱�Ɓv�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ŁA���炩�̖�������������̂ł���m�E�n�E�ł��\�t�g�ł��n�[�h�ł����ł��\�����[�V�����ɂȂ�܂��B �@����ȞB���Ȍ��t���͂т����Ă���̂́A�B���ȃr�W�l�X������Ă���l����������Ƃ������ƂȂ�ł��傤���E�E�E |
|
| �@�g���� | |
| �F�c��ے� | �u�\�����[�V�����Ƃ������t���×����Ă��܂��ˁB�v |
| �փR���T�� | �u�����ł��ˁB���炩�̖�������������̂ł�����\�����[�V�����Ƃ������ƂɂȂ�܂�����E�E�E�v |
| ��c������ | �u���Ⴀ�A�֏��l�܂����������֏��X�b�|�����\�����[�V�����Ƃ������Ƃł��ȁE�E�E�v |
| �V�l���[�R | �i������Đ������͉̂��Ă����̂�����E�E�E�H�j |
| ���t�o | |
�X�|���T�[�����N
Copyright (C)2009 Kazunari Muto. All rights reserved.